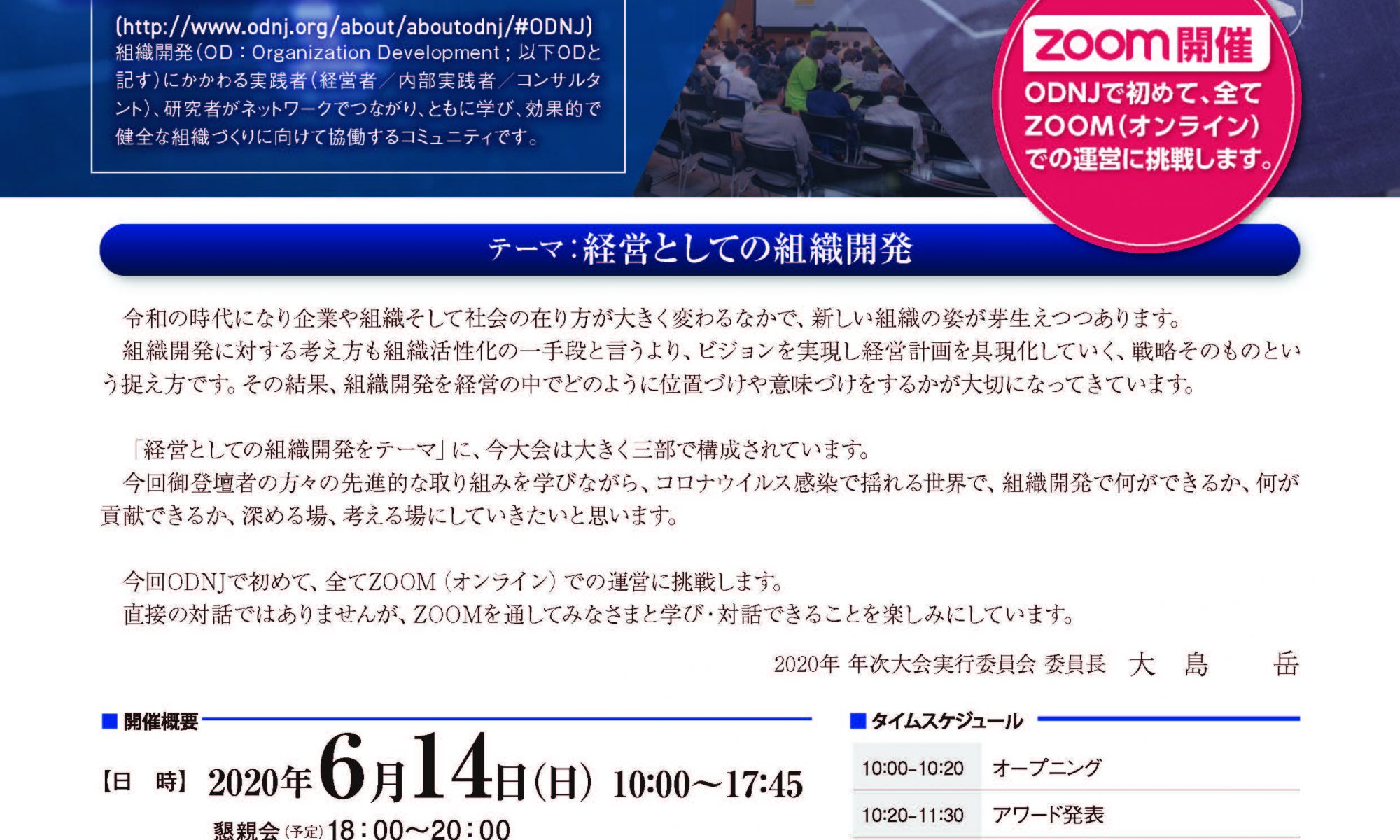先日6月14日(日)、私が理事/事務局長をしているNPO法人ODネットワークジャパン(以下ODNJ)の年次大会&総会が開催されました。
今回は私が大会委員長を務めさせて頂きました。
当初(昨年12月)の時点では外苑前駅近くにあるTEPIA (一般財団法人 高度技術社会推進協会) の会場を借りての、リアル開催を企画していました。しかし2月にはコロナ感染拡大に伴って、リアル+オンラインによるハイブリッドでの開催へと変更しての開催を検討していましたが、3月の時点でコロナの収束が遠いという状況を見てZoomを使用したオンライン開催一本に絞りました。
結果として、「組織開発の対話を大事にしたプログラムがオンラインでここまで出来るんだ」ということを体感し、その可能性を感じることができました。
大会終了後、参加者の方々から
「開催するにあたってどれだけの苦労があったかお察しするとともに、開催していただいたことを感謝します」という温かい言葉を聞くことができました。
また、地方の方からは、「オンライン開催により交通費と時間をとても節約することができ感謝している」との声もいただきました。
年次大会を無事開催することができ、また多くの方のご協力によって成功に終わったことを感謝しております。
実は、年次大会&総会とは別に、もう一つ大きなプロジェクトが進行していました。
それは「コロナの中、今私たちができること」プロジェクトです。
緊急事態宣言が発令されて、改めて組織開発に今何ができるのかを考えていました。
なぜなら、全ての経済活動がストップしてしまったような状況では、残念ながら組織開発に何もできないような無力感を感じていたからです。
そのような中で ODNJの会員で「今私は何ができるのか」を考えました。
そして組織開発ではないけれども、会員の中には多くの専門家がいる。その専門家たちのお力を借りて、この状況下で助け合っていくことはできないだろうかというふうに考えました。
そのことを会員の中の社会保険労務士の方に相談した結果として、全国の他の会員の方も巻き込んで、会員向けに 助成金・補助金そして融資などをいかに活用したらいいかというテーマの勉強会を企画して頂きました。
そのプロジェクトメンバーの中にODNJ中部支部長もいらっしゃいました。
プロジェクトの中で「私たちに何かできること」を真剣に考える姿にインスパイアされ、中部独自としても「今私たちができること」プロジェクトがスタートしました。しかもシリーズで、です。
中部では看護師や心療内科のカウンセラー、そして日本語教師の方といった多彩なメンバーがおり、彼ら彼女らが自分の専門分野でできることを立ち上げてくれたのです。
その他にも、 私が担当する組織開発スキルアップ講座の 受講者OB たちが、同じメンバーだった島根県の精神科医師を主体に、コロナ禍のストレスマネジメントをどう考えるかという勉強会を実施してくれました。
昨年中部は「分科会」から「支部」に昇格し、各地にも地域分科会が発足していました。 ODNJ委員長会では 地域支部や分科会をプラットホームとして活性化して行くつもりでした。そうした方向が、コロナ禍でオンラインでのコミュニケーションしか取れなくなった環境にも関わらず、地域を超え、テーマに共感した渦がどんどん波及していくことが続いていったのです。
これは、私が従来考えていた「戦略ありきの組織化ではなく、共感ベースの組織化」を実体験する場となりました。
はじめに組織ありきではなく、共感を巻き起こすビジョンや価値観を持っていれば、オンラインの中で時間・空間を超えて自己組織化が図れるという、そんな体験です。
この実体験を通して、自分の内在的価値に磨きをかけることがより重要になってくる気がしています。
それを発信して共感の波及ができることによって、従来にない新しい事業ができてくるという新しい未来の出現かもしれません。
大島岳